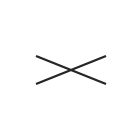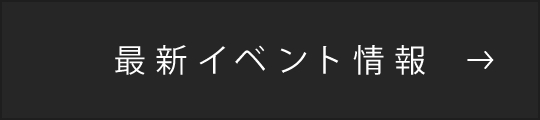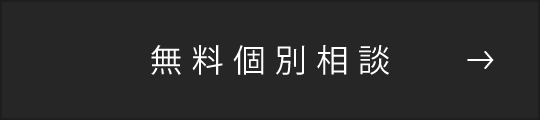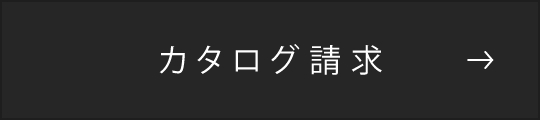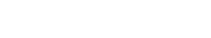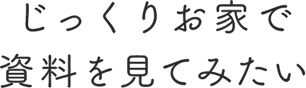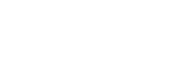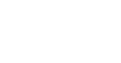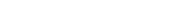「家を建てたいけれど、費用が気になる…」そんな方に朗報!
2025年も、住宅取得を支援するさまざまな補助金や減税制度が用意されています。
上手に活用すれば、建築費の負担を軽減できるだけでなく、省エネ性能の高い快適な住まいを手に入れるチャンスにもなります。
補助金は対象となっている工務店で建てる必要がありますし、減税制度に関しては自身で申請する必要があるものもあります。
これらの支援策には、それぞれ申請の条件や期限が定められています。
内容をよく知らないまま家づくりを進めてしまうと、「もらえるはずだった補助金が申請できなかった…」「減税の対象外だった…」といった残念な結果になりかねません。
そこで今回は、2025年最新の補助金・減税制度に関してお話します。
2025年の最新情報に基づき、住宅取得に関する補助金・減税制度を分かりやすく解説します。
特に注目すべきは、2025年から新たにスタートする制度や内容が更新される制度です。
賢く情報を収集し、お得に家づくりを進めるためのポイントをしっかり押さえていきましょう。
それではご覧ください!
補助金活用のメリットと押さえておくべき注意点
補助金を利用することで建築コストを抑えられるだけでなく、性能の高い住宅を建てるきっかけにもなります。
しかし、補助金には要件があり、適用される条件を満たす必要があります。 また、追加コストや手続きの負担、利用期限の厳守といった注意点もあるため、メリットとデメリットをバランスよく把握することが重要です。
補助金活用のメリット
経済的負担の大幅な軽減
補助金を活用することで、建築費や設備投資の一部が補填され、家計への負担を大きく減らすことができます。
特に、初期費用の高さがネックとなる若者世帯や子育て世帯にとっては、大きな支援となるでしょう。
さらに、補助金を活用した分をメンテナンス費用やインテリアに充てるなど、資金を有効に活用できます。
住宅性能の向上と快適な暮らしの実現
多くの補助金は、省エネ性能や耐震性など、一定の基準を満たす住宅を対象としています。 高断熱材や高効率設備の導入が可能となり、光熱費の削減につながります。
エネルギー消費量が抑えられ、冬は暖かく、夏は涼しい快適な住環境を実現できます。
さらに、補助金要件を満たすために住宅性能を向上させることで、長期的なランニングコスト削減にもつながるでしょう。
補助金活用の注意点
適用要件の確認は必須
すべての住宅が補助金の対象となるわけではありません。 断熱性能、導入する設備、世帯構成(年齢や子供の有無など)といった細かな要件が定められています。 計画段階で、どの補助金が利用できそうか、その要件を満たせるかを工務店やハウスメーカーとしっかり確認しましょう。
要件を満たすための追加コスト
補助金の要件を満たすために、標準仕様からの変更や追加工事が必要となり、結果的に費用が増加するケースもあります。 「補助金をもらうこと」が目的にならないよう、補助金額と追加コストを比較検討し、本当にメリットがあるかを見極める冷静な判断が必要です。
申請手続きと期限の厳守
補助金の申請には、様々な書類の準備や手続きが必要です。 多くの場合、工務店やハウスメーカーが申請を代行してくれますが、施主として協力が必要な場面もあります。 また、申請には期限が設けられており、これを過ぎると受け付けられません。スケジュール管理も重要なポイントです。
【2025年版】注目の新築住宅向け補助金・助成金
国が提供する補助金や助成金には、省エネや環境負荷の低減、子育て支援など目的に応じた制度があります。
それぞれ条件や上限額が異なるため、事前にしっかりと内容を確認しておくことが大切です。
また、複数の補助金を併用できる場合もあるため、条件の重複や申請期間の違いなどにも注意が必要です。
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス補助事業(ZEH)
ZEH(ゼッチ)とは、高断熱や高効率設備、再生可能エネルギーの活用によって、住宅の年間エネルギー消費量を実質ゼロにすることを目指した住宅のことです。一定の基準を満たすことで、最大100万円程度の補助金を受けることができます。
ZEH住宅は、エネルギーコストの削減だけでなく、環境負荷の低減にも貢献できるため、将来的な光熱費の高騰に備えたい人にもおすすめです。
補助対象
- ZEH基準を満たす住宅を新築・購入すること。
ZEH支援事業に登録された工務店・ハウスメーカーでの建築・購入が必要です。
| 対象住宅 | 補助金額 |
|---|---|
| ZEH | 55万円 |
| ZEH+ | 100万円 |
子育てグリーン住宅支援事業 (2025年 NEW)
子育てエコホーム支援事業の後継版。省エネ住宅を建てる場合に利用できる補助金制度です。
子育て世帯だけでなく、すべての世帯が対象になる項目が増えました。
最大160万円程度の補助金を受けられる場合もあります。
補助対象
- 令和6年11月22日以降に、新築の場合は基礎工事後の工程(上棟など)に着手したもの、リフォームの場合は工事に着手したもの。
※子育て世帯等:申請時点で18歳未満の子を有する世帯、または夫婦いずれかが39歳以下の世帯。
| 対象世帯 | 対象住宅 | 補助金額 |
|---|---|---|
| すべての世帯 | GX志向型住宅 |
160万円 |
| 子育て世帯等 | 長期優良住宅 | 80万円(※100万円) |
| 子育て世帯等 | ZEH水準住宅 |
40万円(※60万円) |
給湯省エネ2025事業
エコキュートやハイブリッド給湯機など、高効率な給湯器を導入する際にもらえる補助金制度です。
家庭のエネルギー消費の大きな割合を占める給湯分野において、より省エネな機器への転換を促進し、結果的にCO2削減や光熱費の削減に繋げることを目的としています。最大130万円程度の補助金を受け取ることができます。
補助対象
- 令和6年11月22日以降に高効率給湯器を導入したもの。
子育てグリーン支援事業の補助金を受ける場合は、併用できません。
| 対象性能 | ヒートポンプ給湯器 (エコキュート) |
ハイブリッド給湯器 | 家庭用燃料電池 (エネファーム) |
|---|---|---|---|
| 基本額 | 6万円 | 8万円 | 16万円 |
| ① 昼間の余剰再エネ電気を活用可能・ネット接続 | 10万円 | 13万円 | - |
| ② 5%以上CO2排出量が少ない | 12万円 | 13万円 | - |
| ①+② | 13万円 | 15万円 | - |
| ③ ネット接続・停電対策機能あり | - | - | 20万円 |
【重要】補助金の申請には事業者登録をした工務店、ハウスメーカーが必須
これまで紹介した補助金を申請できるのは、対象の補助金制度に事業者登録をしている工務店、ハウスメーカーで建てた場合に限ります。 つまり、建てた家がZEH基準を満たしていても、工務店、ハウスメーカーが事業者登録をしていなければ申請することができないんです。
ですので、補助金の活用を検討している場合は、契約前の段階で、検討中の工務店やハウスメーカーが希望する補助金制度の登録事業者であるかを確認しておくといいですね。
ベルズワークスが登録している補助金制度
ちなみに、ベルズワークスは…
- ネット・ゼロ・エネルギーハウス補助事業(ZEH)
- 子育てグリーン住宅支援事業
- 給湯省エネ2025事業
上記すべての制度に事業者登録を行っておりますので、これらの補助金申請のサポートはバッチリです! お気軽にご相談ください。
補助金申請の条件と要件
補助金を受け取るためには、申請者自身と建築する住宅の両方が、定められた要件を満たす必要があります。
申請者の主な要件
- 日本国内に居住する個人であること。
- 新築住宅の建築主または購入者であること。
- 制度によっては、年齢(若者夫婦世帯)や子供の有無(子育て世帯)などの要件が加わることがあります。
住宅の主な要件
- 省エネ性能基準(断熱等級、一次エネルギー消費量等級など)を満たすこと。
- 耐震基準を満たすこと。
- 制度によっては、床面積や特定の設備の導入などが要件となる場合があります。
世帯別のポイント
- 子育て世帯: 「子育てグリーン住宅支援事業」のように、子育て世帯を対象とした、より手厚い支援が用意されている場合があります。教育環境や住環境の向上を目的とした制度が多いのが特徴です。
- 若者夫婦世帯: 住宅取得時の初期負担軽減を目的とした支援(例:子育てグリーン住宅支援事業の対象)や、自治体によっては独自の利子補給制度などが設けられている場合もあります。
申請に必要な書類(主なもの)
補助金の申請には、様々な書類の提出が求められます。不備があると審査に時間がかかったり、最悪の場合、申請が受理されなかったりすることもあるため、計画的に準備を進めましょう。
- 施主様にご準備いただく書類(例):
- 本人確認書類(住民票など)
- (住宅ローン利用の場合)金銭消費貸借契約書(ローン契約書)の写しなど
- 工務店・ハウスメーカーが準備・取得する書類(例):
- 建築確認済証の写し
- 工事請負契約書の写し
- 省エネ性能を証明する書類(BELS評価書、性能計算書など)
- 各種補助金の申請書
多くの場合、申請手続きは工務店やハウスメーカーが主体となって進めますが、施主様の協力が必要不可欠です。必要書類の案内があった際には、速やかに対応しましょう。
【見逃せない!】新築住宅に適用される減税制度
新築住宅を建てる際には、補助金だけでなく税制上の優遇措置を活用することで、より大きな経済的メリットを得ることができます。
住宅ローン減税や贈与税非課税措置など、条件を満たせば長期的な家計負担を抑えつつ、資産形成にもつながる点が魅力です。
補助金と組み合わせることで、さらに効率的な家づくりを進められるため、ぜひ一通り確認しておきましょう。
住宅ローン控除
- 概要: 住宅ローンを利用して住宅を取得した場合、年末のローン残高に応じて、所得税(控除しきれない場合は一部住民税)が一定期間(原則最長13年間)還付・減額される制度です。
- ポイント: 控除額はローン残高や住宅の性能(省エネ基準など)によって異なります。長期にわたる恩恵があるため、家計への影響が大きい制度です。入居年や住宅の条件によって制度内容が変わるので金融機関や税務署の情報をチェックしましょう。
贈与税の非課税措置
- 概要: 親や祖父母など直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税になる特例措置です。
- ポイント: 省エネ性能の高い住宅などは、非課税枠が拡大される場合があります(最大1,000万円)。資金援助を受ける予定がある場合は、必ず利用したい制度です。適用には期限や条件があります。
不動産取得税の軽減
- 概要: 土地や建物を取得した際に一度だけ課税される不動産取得税ですが、新築住宅の場合、床面積などの要件を満たすと税額が軽減されます。
- ポイント: 自治体によって軽減内容は異なりますが、数十万円単位での節税効果が期待できます。
固定資産税の軽減
- 概要: 新築住宅に対しては、一定期間(一般住宅は3年間、長期優良住宅などは5年間)、固定資産税が2分の1に減額されます。
- ポイント: 住宅取得後の維持費負担を軽減する上で重要な制度です。特に初期の負担が大きい時期に恩恵を受けられます。
登録免許税の軽減
- 概要: 不動産の所有権保存登記や移転登記、住宅ローンの抵当権設定登記などにかかる登録免許税が、一定の要件(床面積、新築・中古、住宅性能など)を満たすことで軽減されます。
- ポイント: 数万円から十数万円単位で減らせる可能性があります。登記手続きは司法書士に依頼することが多いですが、軽減措置の対象となるか確認しておきましょう。
印紙税の特例措置
- 概要: 不動産の売買契約書や建築工事請負契約書に貼付する印紙税が、契約金額に応じて軽減される場合があります。
- ポイント: 契約時に必要な税金ですが、特例措置により負担が軽くなります。契約金額が大きいほど恩恵を受けやすいため、建築計画の段階で適用条件をチェックしておくことが重要です。
最後に
家を建てる際、補助金や減税制度を活用すれば、大きな費用負担を軽減できます。
しかし、それぞれに申請条件やスケジュールがあるため、事前の情報収集と計画的な準備が重要ですね。
今回ご紹介した制度を上手に活用すれば、建築コストを抑えながら、省エネ性能の高い快適な住まいを実現できます。
「手続きが複雑そう…」と感じるかもしれませんが、補助金の申請手続きの多くは、工務店やハウスメーカーがサポートしてくれます。
施主様ご自身で全てを行う必要はなく、必要な書類を準備するなどのご協力をお願いする形が一般的ですので、過度に心配する必要はありません。
まずは、利用できそうな制度がないか情報収集から始めてみましょう。
そして、信頼できるパートナー(工務店・ハウスメーカー)を見つけ、二人三脚で賢くお得な家づくりを進めていきましょう。
ベルズワークスでは、補助金や減税制度に関するご相談も承っております。
お客様の状況に合わせた最適な活用方法をご提案させていただきますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。